新着情報
車のブレーキの利きが悪いときは要注意!原因から対処法・修理費用まで徹底解説
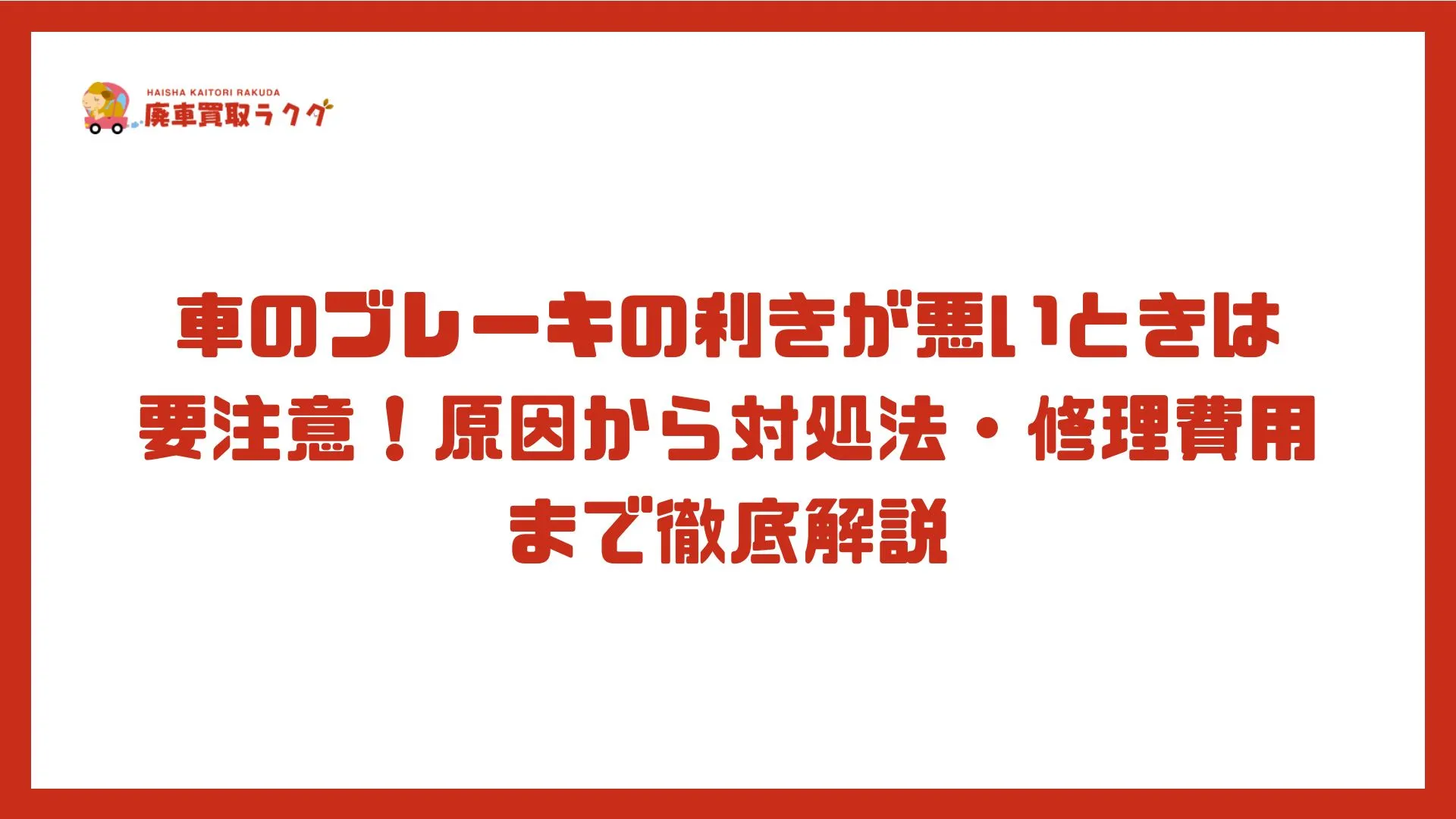
「ブレーキの利きが悪い気がする」「止まるまでの距離がいつもより長い」——そんな違和感を覚えたとき、多くのドライバーは不安を感じるはずです。ブレーキは、車の安全性を左右する最も重要な部品のひとつ。わずかな異常でも放置すれば、重大な事故につながる恐れがあります。
とはいえ、ブレーキの利きが悪くなる原因はさまざまで、整備不要の一時的なものから早急に修理が必要なケースまで幅広く存在します。大切なのは、その違いを正しく見極めることです。
本記事では、ブレーキの利きが悪くなる主な原因や自分で確認できるチェックポイント、応急対処法、そして整備工場での修理費用の目安までを詳しく解説します。安全な走行を守るために、まずは原因を正しく理解しましょう。
車のブレーキの利きが悪いと感じたときの危険性と初期症状
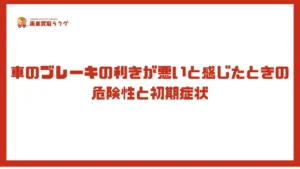
「ブレーキの効きが悪い気がする」と感じた時点で、それはすでに車が発する警告サインです。ブレーキは車の安全を支える中核的な機能であり、ほんのわずかな異常でも放置すれば、走行中の制動距離が伸びたり、制御不能に陥る危険性があります。特に高速走行時や雨天時などは、数メートルの差が重大な事故を生むこともあります。
ブレーキ性能の低下には、「摩耗」「劣化」「油圧不良」などさまざまな要因が関係しますが、ドライバー自身が**“感覚の変化”**を正しく捉えることが、早期発見の第一歩です。
ブレーキの利きが悪くなるときに現れる主な症状
以下のような違和感が一つでもある場合は、ただちに原因を確認する必要があります。
-
ブレーキペダルがいつもより深く沈む
-
踏み込んでも効き始めが遅い
-
ブレーキ時にキーキー・ガリガリと音がする
-
停止直前に車体が片側へ流れる
-
ペダルを踏むたびに振動が伝わる
-
朝や雨の日だけ効きが悪く感じる
これらは一見「よくあること」と思われがちですが、実際にはブレーキ内部の摩耗や油圧低下が進行しているサインである場合も少なくありません。早い段階で気づき、整備士に相談することが、事故を防ぐ最善の方法です。
ブレーキの利きが悪くなる原因とは?
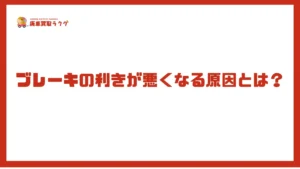
ブレーキの利きが悪くなる原因は一つではありません。
「ペダルが柔らかい」「硬い」「音がする」「片側に流れる」など、症状によって原因が異なるため、まずは自分の車の状態を正しく見極めることが大切です。ここでは代表的なケースを症状別に解説します。
① ペダルが柔らかい・深く沈む場合
ブレーキペダルが以前よりも“ふにゃっ”と沈むように感じる場合、主な原因は油圧系統のトラブルです。
具体的には以下のような可能性があります。
-
ブレーキフルード(ブレーキオイル)の減少・劣化
-
フルードライン内に空気が混入(エア噛み)
-
ブレーキホースやシール部分の微細な漏れ
油圧がうまく伝わらず、ペダルを踏んでも制動力が弱くなる状態です。このまま走行を続けると、ブレーキが突然効かなくなる危険もあります。
→ 対処法は、フルードの量・状態を点検し、必要に応じて交換またはエア抜き作業を行うことです。
② ペダルが硬い・踏み込みにくい場合
ペダルが異常に重く感じるときは、ブレーキブースター(倍力装置)の故障が疑われます。
この部品は、エンジンの吸気圧を利用して踏力を軽減する仕組みですが、負圧ホースの破損や内部の劣化によって機能しなくなると、ドライバーの力だけでブレーキをかける状態になります。
その結果、ペダルが硬く、十分な制動力を得られません。
→ 修理にはブースターやホースの交換が必要で、早めの整備が安全確保につながります。
③ キーキー・ガリガリ音がする場合
ブレーキペダルを踏んだときに「キーキー」「ガリガリ」といった音がする場合は、摩擦部品の摩耗が進行している可能性があります。
-
「キーキー音」:パッドの摩耗が進み、摩擦材が薄くなっているサイン
-
「ガリガリ音」:パッドの摩擦材が完全に削れ、金属同士が接触している状態
このままではディスクローターまで損傷し、修理費用が倍以上に膨らむこともあります。早期のパッド交換が不可欠です。
④ ブレーキ時に車体が片側へ流れる場合
片側に引っ張られるような感覚がある場合は、左右のブレーキ力に差が生じている状態です。
主な原因としては以下が挙げられます。
-
一方のキャリパーピストンの固着
-
パッドまたはローターの片減り
-
タイヤ空気圧の左右差
ブレーキ時に進行方向が乱れ、ハンドル操作を誤るリスクがあります。
→ 点検では、キャリパーの動作確認やパッド交換、タイヤ整備を行います。
⑤ 雨の日や朝だけ効きが悪い場合
一時的にブレーキの利きが落ちる場合は、環境要因による摩擦力の低下かもしれません。
雨天時や朝方はパッドやローターに水分・サビ・汚れが付着し、初期のブレーキが効きにくくなります。
数回ブレーキを踏めば改善するようなら問題ありませんが、異音や感触の違和感が続く場合は、ブレーキ表面の汚れやグリス漏れなどが疑われます。
→ 継続する場合は整備工場で点検を受けましょう。
ブレーキの利きが悪いと感じたときは、「なんとなくおかしい」で終わらせず、症状を具体的に把握することが大切です。次に紹介するのは、自分でも安全に確認できるチェック方法です。
自分で確認できるチェックポイント
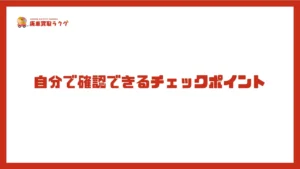
ブレーキの利きが悪いと感じたとき、まずは焦らず安全な場所で簡単なチェックを行いましょう。
整備工場へ行く前に、以下のポイントを確認することで、ある程度の原因を推測できます。
ただし、無理な分解や走行中の確認は絶対に避けてください。
① ブレーキフルード(ブレーキオイル)の量と状態を確認
エンジンルーム内にある「ブレーキフルードリザーバータンク」を見て、液量をチェックします。
「MIN」と「MAX」の間に入っていれば適正ですが、MINライン近くまで減っている場合は要注意です。
-
フルードが減っている → パッドの摩耗や漏れの可能性
-
フルードが濁っている → 劣化または吸湿(交換時期)
ブレーキフルードは湿気を吸いやすく、劣化すると沸点が下がり、ブレーキ性能が低下します。
→ 2年ごとの交換が目安です。
② ペダルの踏み込み感をチェック
エンジンをかけてからペダルを数回踏み、踏み込みの深さと硬さを確認します。
-
「スーッと沈み込む」→ エア混入やフルード漏れの疑い
-
「異常に硬い」→ ブレーキブースター不良の可能性
-
「ポンピングで改善する」→ エア噛みの可能性が高い
この感覚チェックだけでも、整備士に状況を説明する際の重要な手がかりになります。
③ タイヤハウス内のブレーキパッド残量を見る
ホイールの隙間から、ブレーキパッドの厚みを目視できます。
新品時は約10mmほどありますが、3mm以下になったら交換時期です。
ホイールの形状によって見えにくい場合もありますが、
「金属が見えている」「パッドとローターの隙間が狭い」と感じたら、早めの点検をおすすめします。
④ ブレーキ時の音・振動・匂いを感じ取る
走行中に以下のような症状がある場合、早急に点検が必要です。
-
音:「キーキー」「ガリガリ」「ゴーッ」などの異音
-
振動:ペダルやハンドルがブルブル震える(ローターの歪み)
-
匂い:焦げたような臭い(フェード現象・引きずり)
これらは「警告サイン」です。
放置すると重大なトラブルや事故につながることもあります。
⑤ ブレーキ警告灯の点灯
メーターパネルに赤いブレーキランプが点灯した場合は要注意です。
サイドブレーキの引き忘れ以外では、次のような原因が考えられます。
-
ブレーキフルードの低下
-
油圧系統の異常
-
電気系統のトラブル
点灯したまま走行を続けるのは危険です。
→ 安全な場所に停車し、ロードサービスや整備工場に連絡しましょう。
このように、目視や感覚でできる範囲のチェックだけでも、異常の有無をある程度判断できます。
ただし、自分で解決しようと無理に整備するのはNGです。
次の章では、ブレーキの利きが悪いときに整備工場へ持ち込む際のポイントを解説します。
整備工場に依頼する際のポイント
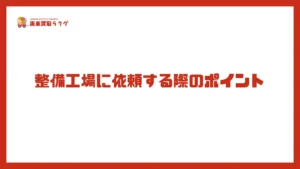
ブレーキの利きが悪いときは、できるだけ早く整備工場へ持ち込むことが安全の第一歩です。
ただし、いざ依頼しようとすると「どんな不具合をどう伝えればいいのか」「修理費用はいくらくらいかかるのか」が気になる方も多いでしょう。
ここでは、実際の依頼手順と注意点を具体的に解説します。
① 点検・修理の依頼先は「認証工場」または「ディーラー」がおすすめ
ブレーキ系統は命に関わる重要保安部品のため、信頼できる整備士に任せる必要があります。
選ぶ際は以下のような業者を基準にしましょう。
-
国土交通省の認証工場・指定工場であること
-
国家資格を持つ自動車整備士が在籍している
-
点検・交換部品を事前に説明してくれる
-
見積もりが明確で、追加費用が発生しにくい
格安修理を謳う業者の中には、非純正品を使用したり、簡易的な修理で済ませるケースもあります。
「安さ」よりも「安全性」と「整備履歴の残る信頼性」を優先しましょう。
② 依頼時は「症状の出方」を具体的に伝える
整備士に正確に伝えるためには、「いつ・どんなときに・どう感じたか」を整理しておくとスムーズです。
たとえば以下のように具体的に伝えると、原因の特定が早まります。
-
「朝の冷間時だけペダルが硬い」
-
「坂道で止まりにくい」
-
「ブレーキを踏むと左に流れる」
-
「踏むたびにキーキー音が出る」
また、「最後にブレーキフルードを交換したのはいつか」「車検からどれくらい経過しているか」も重要な情報です。
症状+経過時間+使用状況を明確に伝えることで、正確な診断につながります。
③ 修理費用の目安
ブレーキ関連の修理費用は部位や症状によって大きく変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 修理内容 | 費用目安(税込) | 作業時間の目安 |
|---|---|---|
| ブレーキパッド交換(前輪) | 約10,000〜20,000円 | 1時間前後 |
| ブレーキローター交換 | 約20,000〜40,000円 | 2時間前後 |
| ブレーキフルード交換 | 約5,000〜10,000円 | 30分程度 |
| ブレーキキャリパー交換 | 約30,000〜60,000円 | 2〜3時間 |
| ホース・配管修理 | 約10,000〜30,000円 | 症状により異なる |
軽自動車・普通車・輸入車によっても金額は異なります。
複数の整備工場に見積もりを取り、相場を把握してから依頼するのがおすすめです。
④ 修理後に確認すべきポイント
修理が終わったあとも、以下の点を確認しておくと安心です。
-
修理内容・交換部品の説明を受けたか
-
使用した部品が純正品かどうか
-
テスト走行を行い、ブレーキの効き具合を確認したか
-
領収書・整備記録簿に内容が記載されているか
これらをしっかりチェックしておけば、次回以降の点検や車検でも履歴として活用できます。
⑤ 修理後も違和感が残る場合の対処法
修理後も「まだ効きが弱い」「ペダルがフワフワする」と感じる場合は、再度点検を依頼しましょう。
ブレーキは複数の部品が連携して動作しているため、一部を修理しても他の箇所に問題が残っているケースもあります。
「様子を見る」で終わらせず、整備士と一緒に試運転を行うことが大切です。
このように、ブレーキの利きが悪いときの整備工場選びや依頼の仕方を理解しておくことで、安全性と費用の両立が可能になります。
次は、実際に整備で改善した成功事例を紹介し、よりリアルなイメージを持てるよう解説します。
ブレーキの利きが悪かった車が改善した実例
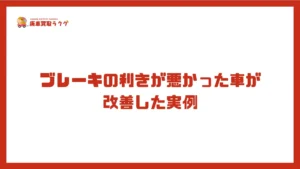
実際に「ブレーキの利きが悪い」と感じていたドライバーが、整備や部品交換によって改善したケースを紹介します。
実例を知ることで、どのような原因が多く、どのような対処で改善するのかを具体的にイメージできます。
事例① ブレーキパッドの摩耗による制動力低下(走行距離8万km)
症状:
・ブレーキを踏んでも止まるまでの距離が伸びた
・ペダルを踏み込むと「キーキー」と高音が鳴る
原因:
ブレーキパッドの摩耗。厚さが1mmを切っており、金属部分がローターに接触していた。
対処:
前輪・後輪のパッドをすべて交換。ブレーキローターも軽度の削れがあったため研磨を実施。
結果:
制動距離が短くなり、音も解消。
整備士から「早期に交換していればローター交換まで行かずに済んだ」との助言。
➡ 定期点検でパッド残量を確認することの重要性を実感した事例です。
事例② ブレーキフルードの劣化による効きの悪化(5年未交換)
症状:
・ペダルを踏むとフワフワした感触
・長い下り坂で効きが急に弱まる
原因:
ブレーキフルードが劣化して水分を多く含み、沸点が低下してベーパーロック現象を起こしていた。
対処:
ブレーキフルードを全量交換し、エア抜き作業を実施。
結果:
ペダルの踏み応えが改善し、安定した制動力を回復。
費用は約7,000円と比較的安価で済んだ。
➡ 定期的なフルード交換(2年ごと)が事故防止につながる典型的な事例。
事例③ ブレーキキャリパーの固着による片効き(片輪だけ熱を持つ)
症状:
・走行後、左前輪だけ異常に熱い
・ブレーキ時に車体が左に流れる
原因:
キャリパーピストンのサビや汚れによる固着で、左側ブレーキが常に引きずり状態に。
対処:
キャリパーの分解清掃とピストン交換を実施。ローターも交換。
結果:
制動時の偏りが解消し、燃費や走行安定性も改善。
費用は約4万円ほど。
➡ 走行後に片輪だけ熱を持つ場合は、キャリパー固着を疑うべきと分かる事例。
事例④ ABSセンサー不良による制御の乱れ(警告灯点灯)
症状:
・ブレーキ時に「ガガガッ」と異音
・ABSランプが点灯したまま
原因:
車輪速センサー(ABSセンサー)の不良。誤作動で制御が乱れていた。
対処:
故障したセンサーを交換(部品代約8,000円、工賃約1万円)。
結果:
ブレーキの挙動が安定し、警告灯も消灯。
➡ 電子制御系の異常は放置せず早めに診断機でチェックすることが重要。
このように、ブレーキの利きが悪い原因は多岐にわたりますが、
早期発見と適切な整備で、ほとんどのケースは改善可能です。
次の章では、こうしたトラブルを未然に防ぐために知っておきたい注意点と予防策を解説します。
ブレーキトラブルを防ぐための注意点と予防策
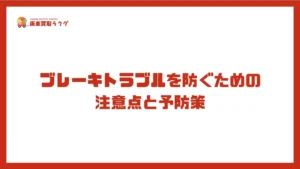
ブレーキの利きが悪くなる原因の多くは、「劣化」と「メンテナンス不足」です。
日常的な点検や定期整備を怠らなければ、重大なトラブルは防ぐことができます。
ここでは、ブレーキを長持ちさせ、安全に走行を続けるための具体的な予防策を紹介します。
① 定期的にブレーキフルードを交換する
ブレーキフルードは走行中に熱を受けやすく、時間とともに水分を吸収して性能が低下します。
交換の目安は2年ごと、または車検ごとです。
特に山道や坂道を多く走る車は、ブレーキ温度が上がりやすく、フルードの劣化も早まります。
【ポイント】
フルードが濁っている、または減っている場合は早めに整備工場で交換を依頼。
② ブレーキパッド残量をこまめに確認する
パッドは走行距離や運転スタイルによって摩耗速度が大きく異なります。
以下の目安を参考に、定期的な点検を行いましょう。
| 車種 | パッド交換の目安走行距離 | 交換時期の目安 |
|---|---|---|
| 軽自動車・小型車 | 約30,000〜40,000km | 2〜3年ごと |
| 普通車・ミニバン | 約40,000〜60,000km | 3〜4年ごと |
| 輸入車・スポーツ車 | 約20,000〜30,000km | 2年ごと |
ブレーキの鳴きや粉の増加も、パッド摩耗のサインです。
③ 長い下り坂では「エンジンブレーキ」を活用する
下り坂でフットブレーキを多用すると、摩擦熱によりブレーキが一時的に効かなくなるフェード現象が起こることがあります。
これを防ぐためには、シフトを「L」や「2」に入れてエンジンブレーキを併用するのが有効です。
【注意】
AT車でもマニュアルモードやギア固定を活用することで、ブレーキ負担を軽減できます。
④ 雨の日や洗車後はブレーキの“初期効き”に注意
雨天や洗車直後は、ブレーキローターやパッド表面に水分が付着し、一時的に制動力が低下します。
出発直後は軽くブレーキを踏みながら走行し、水分を飛ばしてから本格的に走ると安全です。
⑤ 定期点検を怠らない(12か月点検・車検の重要性)
「まだ効くから大丈夫」と油断せず、定期点検を確実に受けることが最も重要です。
プロの整備士は、ドライバーが気づきにくい異常(キャリパー固着・ホース劣化・ローター摩耗など)も見逃しません。
とくに中古車や長期保有車は、半年〜1年ごとの点検を推奨します。
⑥ 急ブレーキ・片足ブレーキの癖を減らす
運転の仕方もブレーキの寿命に影響します。
急ブレーキや、右足を常にブレーキペダルに乗せた「片足ブレーキ」は、
パッドの摩耗・キャリパー固着・燃費悪化の原因となります。
「車間距離を保ち、滑らかな減速を心がける」
これだけでもブレーキの寿命は大きく延びます。
このような基本的なメンテナンスと運転習慣の改善を意識するだけで、
ブレーキの性能を長く保ち、安全運転を続けることが可能です。
まとめ・次にやるべきこと
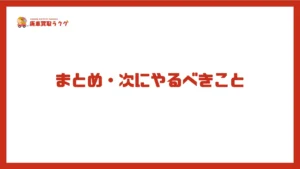
車のブレーキは、命を守る最も重要な装置です。「ブレーキの利きが悪い」と感じたら、軽視せずに早めに原因を特定することが安全運転の第一歩です。
本記事で解説したポイントを整理すると、以下の通りです。
-
症状の確認:ペダルの踏み込み感、異音、振動、片効きなど、違和感は放置せず記録する。
-
原因の把握:摩耗、油圧不良、キャリパー固着、電子制御系の異常など、症状別に原因を想定する。
-
安全なセルフチェック:ブレーキフルードの量やパッド残量、警告灯など、自分で確認できる範囲をチェックする。
-
整備工場への依頼:認証工場やディーラーで正確な点検・修理を受ける。症状や経過を具体的に伝える。
-
予防策の実施:定期点検、フルード交換、パッド点検、急ブレーキの回避など、日常的に安全を意識する。
ブレーキトラブルは放置すれば事故につながる可能性がありますが、早期対応と適切な整備でほとんどの場合改善可能です。
▶ 次にやるべきこと:
-
違和感がある場合は、安全な場所で簡単なチェックを行い、異常があればすぐに整備工場へ相談
-
定期点検やフルード交換、パッド残量確認など、予防メンテナンスを習慣化する
これらを実践することで、車のブレーキ性能を長く保ち、安心して走行できる状態を維持できます。
安全運転のためにも、違和感を感じたら迷わず行動することが大切です。

廃車・車買取の事なら買取ラクダへご相談ください!






